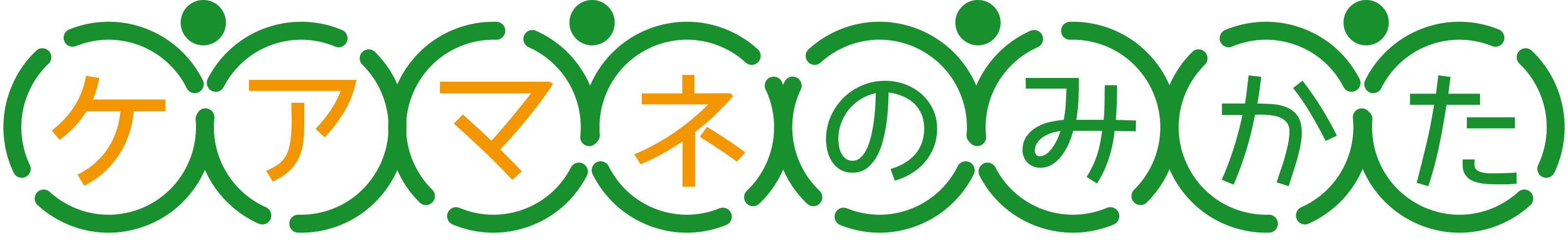介護保険以外の制度や保険外サービスに関する疑問にお答えします
- 2025年8月7日
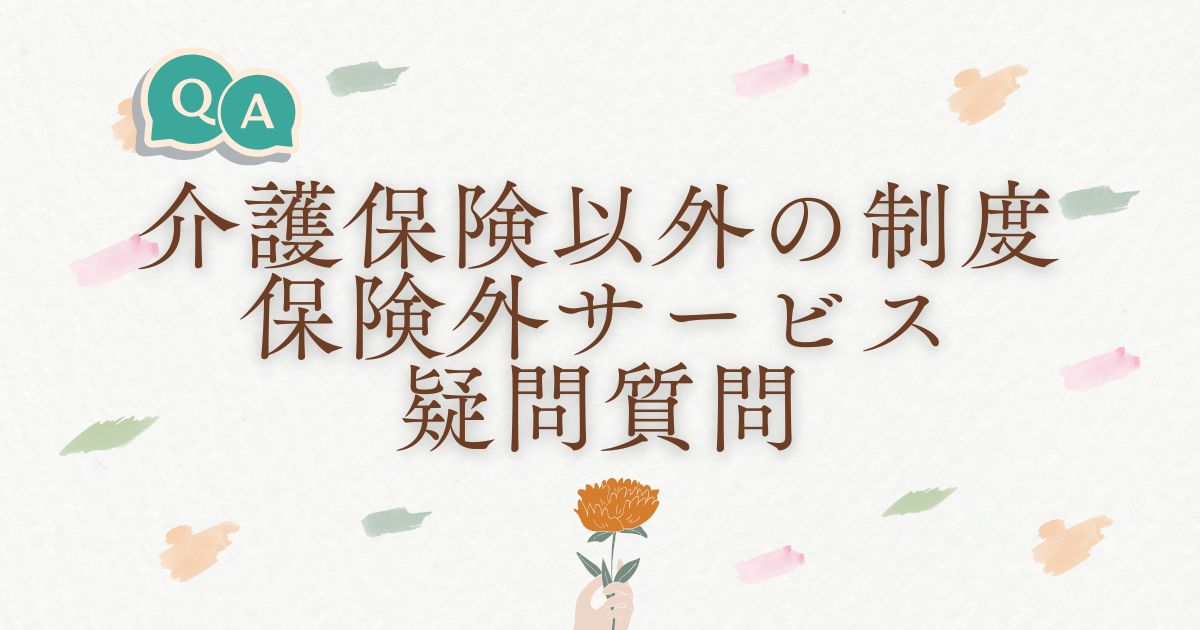
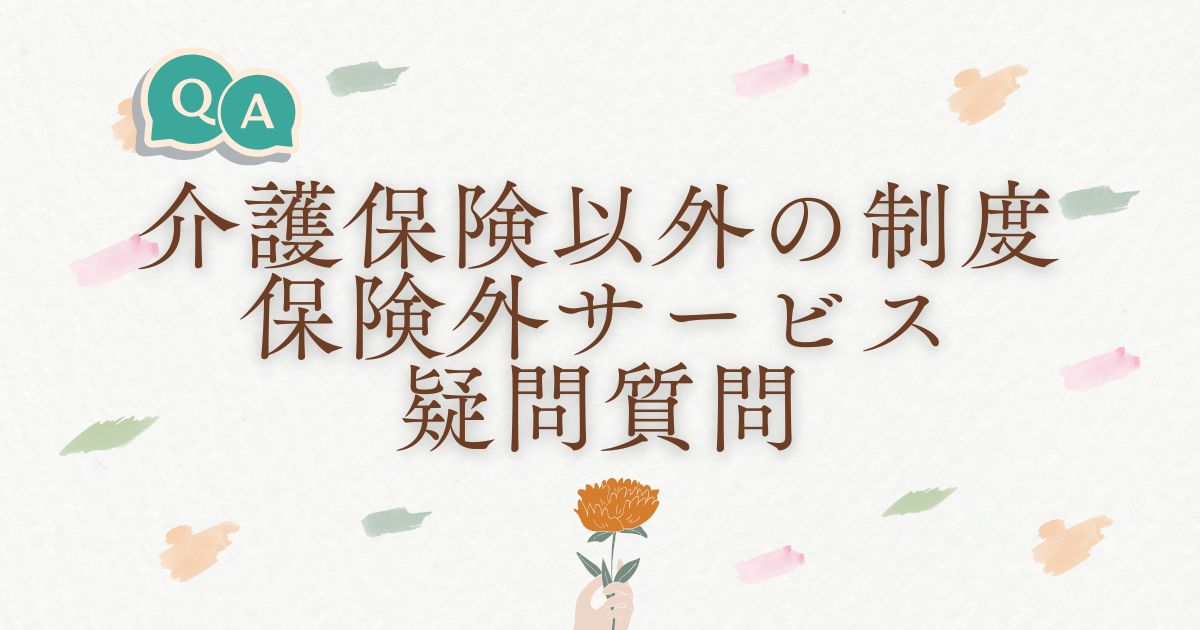
介護保険以外の制度や保険外サービスに関しての疑問は、意外に多いものです。
ケアマネジャーにとっては専門外の分野なので、どこまでかかわればいいのかも迷ってしまいますよね。
この記事では、ケアマネ業務における、介護保険以外の制度に関する疑問やお悩みをご紹介します。
介護保険外サービスとは


介護保険以外のサービスとは、介護保険の適用外となる支援サービスのことです。
たとえば、家事代行や見守り、外出の付き添いなど。
また、自治体やNPOが提供する福祉サービス、医療費助成、生活保護、障害福祉サービスなどが含まれる場合もあります。
ケアマネジャーとしてのかかわり方に戸惑いを感じるケースも多いようです。
【Q1】保険外の介護サービスに関する知識や情報収集の方法がわかりません


難病や精神障害など、公費支援の制度が覚えきれません。
皆さんその都度、膨大な資料をあたり、探してファイリングしているのでしょうか?
—A1. 情報や支援の方法を把握しておくことが重要
ご利用者の生活に精通するケアマネジャーとして、介護保険以外でも適切なサービスにつなげられるよう、情報や支援の「ありか」を知っておくことが大切です。
難病や精神障害者の医療費助成制度などは、どのようなものがあるのか日ごろから注意しておきましょう。
【情報収集のポイント】
情報収集や利用方法を、ケアマネジャーがすべて引き受ける必要はありません。
必要であれば、地域包括支援センターを上手に活用しましょう。
地域包括支援センターは、介護予防支援だけではなく、介護保険制度も含めて福祉の総合相談支援の役割も担っています。
また精神疾患の場合には、保健師に相談しましょう。
誰に聞けばより深くわかるのか、自分なりの情報収集や確認ルートをつくっていくと今後にもつながっていくはずです。
【Q2】生活保護や成年後見など、ケアマネジャーの職務範囲を超える対処法は?
独居の方などは、ケアマネジャーからソーシャルワーカーに相談すると、それからずっと窓口のようになってしまうことがあります。
ケアマネジャー以外のことは不慣れなので、余計な仕事が増えてしまいます。
どこまでケアマネジャーがかかわるべきでしょうか?
—A2. ケアマネジャーの役割は、ご利用者を適切な制度やサービスにつなげること
ケアマネジャーには、ご利用者の日々の生活全般が見えています。
もしも介護保険制度だけでご利用者の生活が守れないと判断したら、必要に応じた制度やサービスを活用しなければならないこともあるでしょう。
- 生活保護制度
- 日常自立支援事業
- 成年後見制度 など
「自分がなんでもやらなくては」と、多くのことに深入りしてしまうケアマネジャーも少なくありません。
その結果「窓口」的な役割も兼ねてしまうケースも多々あるでしょう。
ケアマネジャーがするべきことは、ご利用者を必要な制度やサービスにつなげることです。
生活保護なら、まずはご家族の同意を得て、ソーシャルワーカーとコンタクトをとります。ソーシャルワーカーにつないだ後はご利用者の生活に変化はないか目配りしつつ、情報を共有することで日々の支援をしていきましょう。
【Q3】介護保険外サービスでは、どの制度が優先されますか?


介護保険以外の制度を利用している場合や、障害者手帳を所持しているご利用者の場合、どの制度が優先されるのかいまだにわかりません。
—A3. どちらにもあるサービスを利用する場合は介護保険が優先されるが、注意点も!
障害者手帳を持っているご利用者は、介護保険サービスと障害福祉サービスの両方が利用できますが、ホームヘルプなどどちらにもあるサービスを利用する場合は介護保険が優先されることになっています。
ただし、介護保険給付で適切な支援が受けられるかどうかは、判断がわかれるケースもあります。そのような場合は、適切な制度を利用できるように市区町村の障害福祉担当部署と連携をとりましょう。
また介護保険にはない障害福祉固有のサービスや移動支援など、各地域で実施している生活支援事業の利用については、ケアマネジャーが判断するのは難しいと思われます。市区町村や社会福祉協議会に確認してみましょう。
※64歳以下で生活保護受給者は、障害サービスが優先されます。またヘルパー支援でも、障害サービスのみの内容「美容院やレクリエーションなどの移動支援」は、状況によっては障害サービスが利用できる場合もあります。
【Q4】家事代行などの自費サービス事業者の情報収集方法がわかりません


地域の社会資源の情報がなかなか手に入りません。
役所がもっている情報以外は、どうやったら入手できますか? こちらから営業に行かないとダメなんでしょうか?
—A4. 地域包括支援センター等へ問い合わせを
地域の社会資源についての情報収集は、地域包括支援センターに問い合わせるほか、公民館やボランティアセンターでも情報を得られます。
また自治体によっては自治体自身(またはその委託先)が地域資源の情報をまとめ、Webサイトや小冊子で発行しているところもあるので確認してみましょう。
民間の家事代行サービス情報は、最近は各社のホームページも充実しています。「家事代行 自治体名」などで検索してみてください。
【Q5】地域資源のネットワークづくりのコツは?


地域のケアマネで連絡を取り合って情報を共有しようとしても、なかなかネットワークを築けません。
うまくいくコツはありますか?
—A5. 自治体のネットワークへ参加したり、自身で立ち上げたり
ケアマネジャー同士で地域資源などの情報交換ができるネットワークは、ふだん事業所のメンバーとしか交流のないケアマネジャーにとって有益なものです。
【自治体の施策への参加や、ネットワークの立ち上げもおすすめ】
自治体が音頭をとり、ネットワークづくりに力を入れているところもあります。
もし自分たちでネットワークを立ち上げるのであれば、まずは有志が参加する小さな集まりから始めましょう。
かけ声ばかりでなかなか具体化しない場合は、自分が発起人となることもひとつの手です。
イニシアティブをとれる人(発起人)が議題を用意するなどして、限られた時間をうまく使っていきましょう。
課題を共有して意見を交わすことで、皆が成長し、少しずつでも集まりを拡大していくことが大切です。
小さな集まりから始めて、限られた時間内で密度の濃い集まりにしていきましょう。
介護保険以外の制度やサービスは情報を収集して適切な判断を
介護保険以外の制度やサービスを利用する際には、ケアマネジャーの任務以外となる部分もあります。
ふだんからアンテナを張ってさまざまな情報を収集し、その都度適切な判断ができるようにしておきましょう。