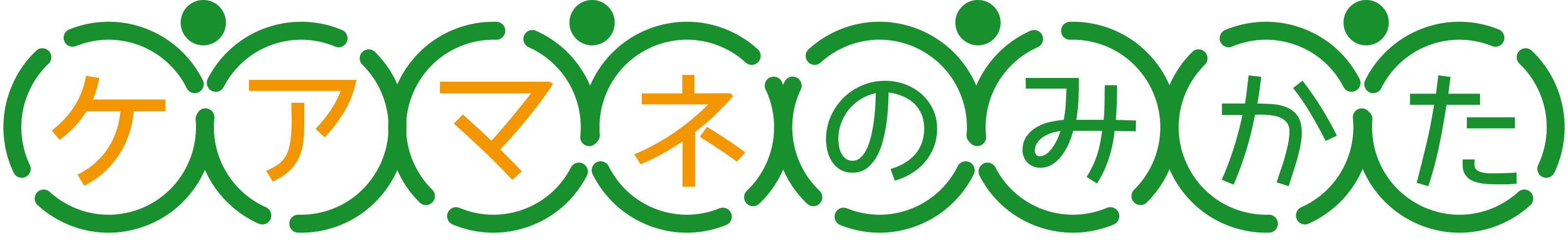医療との連携が苦手?ケアマネジャーの疑問や不安にお答えします
- 2025年8月7日
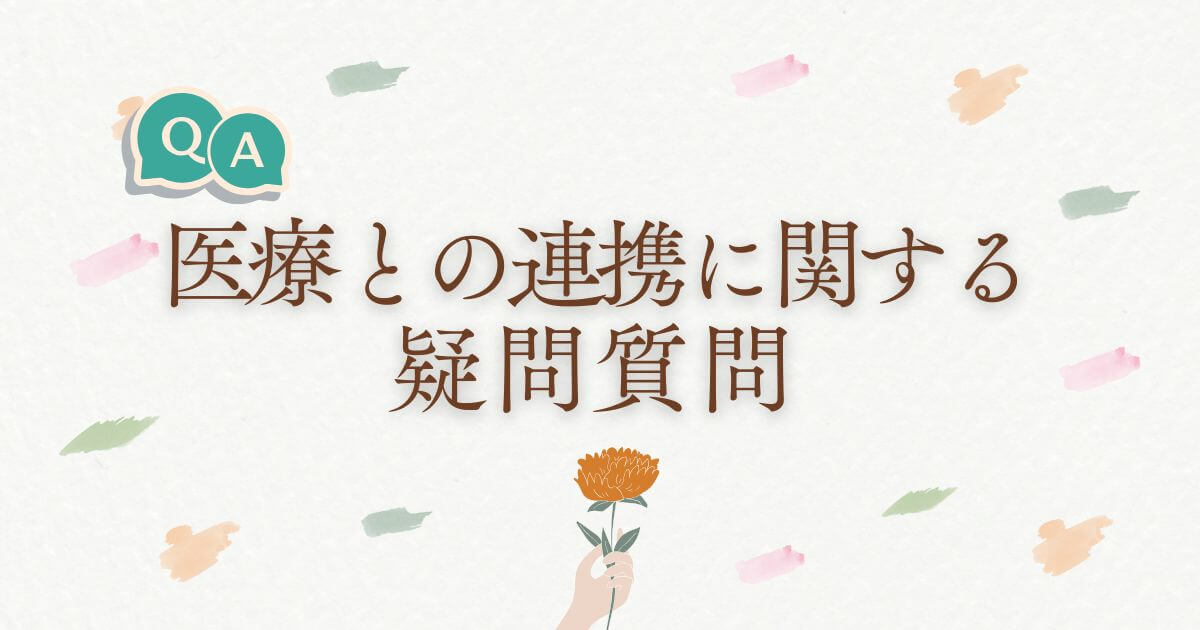
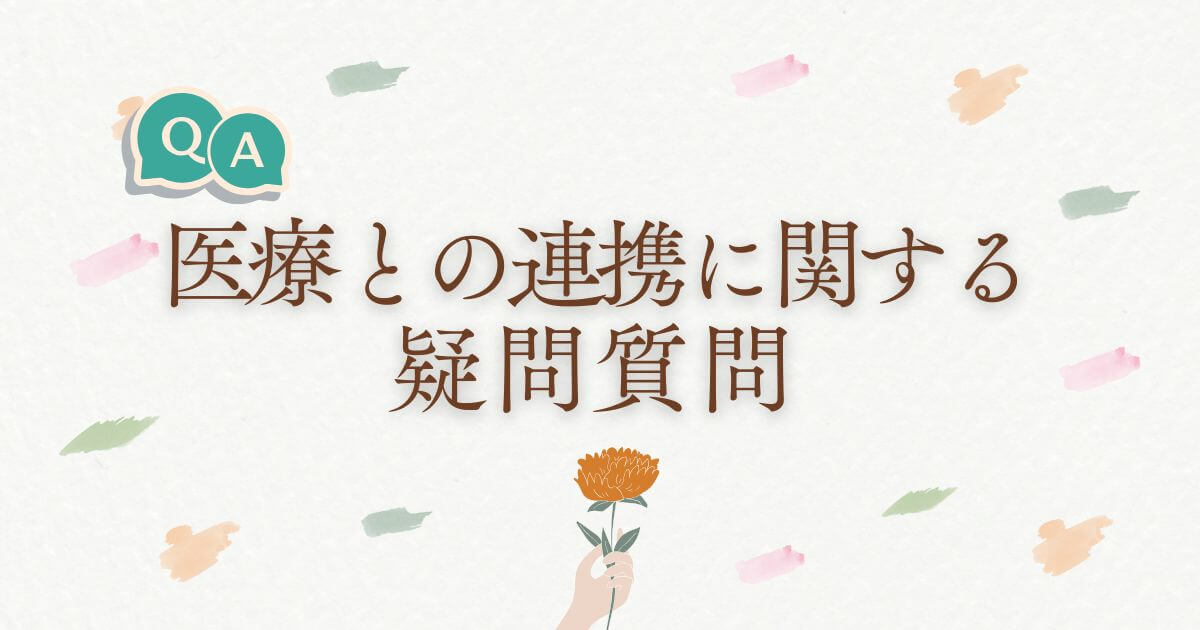
医療と介護の連携は、以前よりは改善されてきたものの、まだまだ課題もあります。
そのため医療連携の場で、戸惑いをもつケアマネジャーも多いようです。
この記事では、ケアマネジャーが医療との連携について抱く疑問やお悩みをご紹介します。
医療との連携が必要な理由とは
介護が必要な高齢者の生活には、介護も医療もどちらもかかせないケースがほとんどです。
しかしそれぞれが孤立しているのでは、思いどおりの治療やサービスが受けられません。
そのため日々の生活や健康状態を把握しているケアマネジャーと、医療機関との連携が必要不可欠となるのです。
【Q1】医療連携の必要性はわかるものの、どうも苦手です


じつはケアマネジャーで、医療との連携に苦手意識をもっている人は多いようです。
その理由には以下のようなものがあげられます。
- 医療の知識が少ない
- 医療機関との接点がない
- 医師や医療従事者と意思疎通がしづらい
—A1. ケアマネジャーとして適度なプライドをもち、同じ目的意識で
先入観からの苦手意識はもたずに、ケアマネジャーとしての立場で対応をすれば大丈夫です。
医療連携では、医師とのかかわりは避けられません。
しかし医療従事者とかかわる際に、電話や文書などでのやりとりが多く、余計に苦手と感じるケースもあります。
医療も介護もご利用者にとっては、かかせません。一人ひとりのご利用者にとって何が一番いい治療やケアなのかを、それぞれの立場で同じ目的意識をもって仕事をすることが大切です。
「医師が苦手で」と感じるケアマネジャーもいるかもしれませんが、臆することなくケアマネジャーとしての適度なプライドをもつことも必要でしょう。
【Q2】ケアマネジャーにとって医療連携で大切なことはなんですか?


医療連携をする際に、ケアマネジャーとして大切なポイントを教えてください。
—A2. 最低限の医療知識とケアマネジャーとしての情報のやりとりです
医療連携する際には、ケアマネジャーならではの強みが必要とされます。
ケアマネジャーの強みとは、ご利用者のふだんの状態などをしっかりと把握しており、それを的確に医師や医療従事者へ伝えることです。
また医療から受けた情報をもとに、今後しなければならないことをご利用者やご家族へ伝え、利用するサービスの準備を進めます。
ときにはケアマネジャーとしての仕事をしているだけでは、医療とのコミュニケーションがうまく進まないこともあるでしょう。
ケアマネジャーとして大切なことは、ふだんから最低限の医療知識を備えておくことです。
医師や医療関係者の言っていることがまったく理解できないのでは、スムーズな連携ははかれません。
【Q3】医師や看護師、MSWなど医療従事者とのかかわり方がわかりません


医師や看護師、MSW(メディカルソーシャルワーカー)などの医療従事者とのかかわり方がわかりません。
ご利用者の生活支援のためには、どうすればいいですか?
—A3. 医療従事者ともよい関係を築く努力を心がけましょう
介護と医療の連携では、違う職種が互いの専門性を尊重し、情報を共有しながらご利用者の支援という同じ目的に向かって協力します。
ケアマネジャーはご利用者の介護支援の専門職であり、支援の道筋をつくるコーディネーターです。
そのうえで医療従事者の話す内容をきちんと聞き、理解するように努めます。医師やナース、MSWにも積極的に働きかけ、よい関係を構築する努力をしましょう。
また医師が専門分野をもつケースも多々あります。いつもはがんの治療でかかっている医師に、褥瘡はみてもらえないケースもあるでしょう。
そうした場合には、ケアマネジャーはご利用者に適した主治医を探して提案をします。
【Q4】疾患に対する知識がなく不安です
医療従事者から略語で説明されたときに聞き返すと「勉強不足」と思われるし、知ったかぶりもできず、いつも困ってしまいます。
かといって体系的に勉強する時間もソースもありません。
ケアマネはどのくらい医療知識があればいいのでしょうか? また、知識を身につけるよい方法はありますか?
—A4. ケアマネに必要な医療知識は、基本的な人体のしくみ、高齢者の体の特徴、かかりやすい疾患など
たとえ勉強していたとしても、医療でわからないことはたくさんあります。
もしも医療従事者の用語がわからないときには、その場で確認しましょう。
専門知識のある人に聞くことは、恥ずかしいことではありません。
また一度聞けば、知識が自分のなかに定着していきます。
自分は何がわかり、何がわかっていないかを知っておくことも大切です。
ケアマネジャーとして知っておきたい医療知識のおもなものには、以下があります。
- 基本的な人体のしくみ
- 高齢者の体の特徴
- かかりやすい疾患
一度には無理でも、繰り返し学んでいけば必ず十分な知識が身に着きます。
家庭の医学事典を1冊購入する、必要に応じてネットで検索するなど、気になることはすぐに調べる癖をつけましょう。
【医療従事者にご利用者の身体状況を伝えることも大切】
医療従事者に対して、ご利用者の身体状況の変化を伝えることは介護の専門職として大切な仕事です。
ご利用者の支援という同じ目的に異なる専門職同士で会話が進み、知識も身に付き、結果としてコミュニケーションが円滑になります。
介護の専門職として、医療の専門職に働きかける努力は惜しまないようにしましょう。
ケアマネジャーは医療と信頼関係を構築しスムーズな連携を


ケアマネジャーの立場で、医療連携の際に心がけることを紹介しました。
ご利用者やご家族が安心して暮らせるためには、医療と介護の連携はかかせません。
むだに苦手意識をもつことなく、つねに知識を身につける努力を怠らず、介護のプロとして情報を共有すればスムーズな連携がはかれるでしょう。