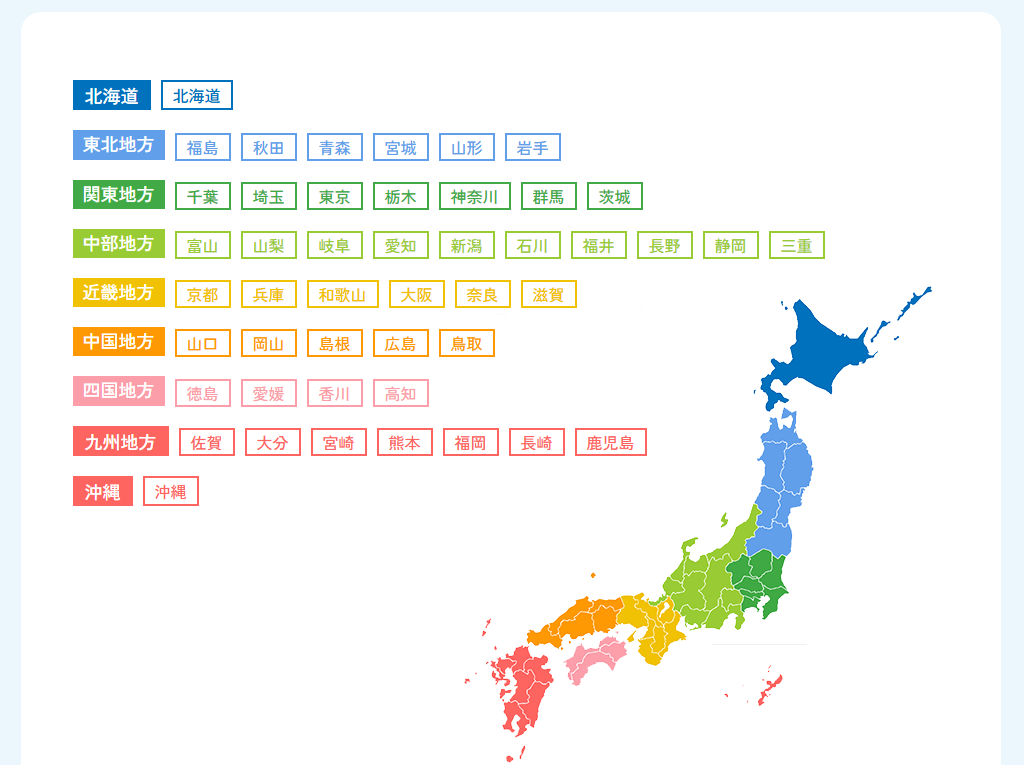多くの人が「入院」と聞くと、病気や怪我を治療し、元気になって退院する姿を思い浮かべるでしょう。
手術を受け、集中的な治療によって苦痛から解放される場所。それが病院の一般的なイメージです。
しかし、その一方で、入院という特殊な環境が、治療対象の疾患とは全く別の、新たな機能低下を引き起こす可能性があることは、あまり知られていません。
「肺炎はすっかり良くなったはずなのに、なぜか歩けなくなってしまった」
「手術は成功したと聞いたのに、トイレに一人で行けなくなってしまった」
このような、一見すると不可解な事態は、決して稀なことではありません。
これこそが、医学の世界で深刻な課題として認識されている「入院関連機能障害(Hospitalization-Associated Disability:HAD)」と呼ばれる状態です。
HADは、特に身体的な予備能力が低下している高齢者において、顕著に現れる傾向があります。
研究によれば、70歳以上の高齢者のうち、実に30%から60%もの人々が、入院をきっかけに何らかの日常生活動作(ADL)に支障をきたし、退院後もその影響が残ると報告されています。
これは、病気そのものの後遺症ではなく、「入院生活」そのものが原因となって生じる、いわば「医原性(いげんせい)」の障害とも言えるのです。
入院前の自立した生活が一変し、退院後には介助や介護が不可欠となる……この現実は、ご本人の尊厳や生活の質(QOL)を著しく損なうだけでなく、ご家族にとっても精神的、身体的、そして経済的に大きな負担を強いることになります。
さらに、介護保険制度や医療財政を圧迫する一因となり、高齢化が急速に進む日本社会全体にとって、避けては通れない喫緊の課題となっています。
この記事では、もはや他人事ではないHADについて、その定義から原因、そして最も重要な「予防策」に至るまで、多角的に、そして深く掘り下げて解説します。
なぜ入院が機能低下を招くのか、そのメカニズムを理解し、本人、家族、そして医療者が一体となって取り組める具体的な対策を明らかにしていきます。
あなたの、そしてあなたの大切な家族の未来を守るために、ぜひ最後までお読みください。
入院関連機能障害(HAD)の正体
HADの定義 失われる「当たり前の日常」
HADをより正確に理解するために、その定義を詳しく見ていきましょう。
HADとは、「入院時に自立していた日常生活動作(Activities of Daily Living:ADL)の一つ以上が、退院時に介助を要する状態になること」と定義されます。
ここで重要なのが「ADL(日常生活動作)」という概念です。
ADLとは、私たちが日常生活を送る上で不可欠な、基本的な身体活動を指します。具体的には、以下の項目が含まれます。
・食事:自分で箸やスプーンを使って食べ物を口に運ぶこと。
・整容:顔を洗う、歯を磨く、髪をとかすなど、身だしなみを整えること。
・更衣:自分で衣服の着脱を行うこと。
・トイレ動作:トイレまで移動し、排泄、後始末を自分で行うこと。
・入浴:浴槽をまたぐ、体を洗うなど、一連の入浴動作を行うこと。
・移動:ベッドから起き上がり、歩行する、車いすへ乗り移るなど、自分の力で移動すること。
HADは、これらの「当たり前」にできていたはずの動作が、入院というイベントを境に、一つ、また一つと失われていく状態なのです。
さらに、ADLよりも高次な生活機能を示す「IADL(Instrumental Activities of Daily Living:手段的日常生活動作)」という概念も存在します。
これには、買い物、食事の準備、服薬管理、金銭管理、電話の使用、交通機関の利用などが含まれます。
HADはまずADLの低下として現れることが多いですが、進行するとIADLにも影響が波及し、地域社会での自立した生活がより一層困難になります。
HADの深刻さは、その発生率の高さにあります。前述の通り、高齢入院患者の約3分の1がHADを発症するとされ、疾患や重症度に関わらず、誰にでも起こりうる普遍的なリスクなのです。
急性期医療が目覚ましい進歩を遂げ、多くの命が救われるようになった現代だからこそ、その裏で静かに進行するHADという問題に、私たちは真剣に向き合う必要があります。
なぜ起こるのか? 入院生活という「非日常」の罠
では、なぜ治療の場であるはずの病院が、機能低下を招くのでしょうか。
その答えは、入院生活が持つ特有の環境に隠されています。
〇徹底された「安静」という名の不動
治療において安静は重要ですが、過度な安静は諸刃の剣です。
点滴や心電図モニター、ドレーン(体液を排出する管)などが体に繋がれていると、患者は心理的にも物理的にも動きづらくなります。
また、医療現場では「転倒=医療事故」と捉える傾向が強く、安全を最優先するあまり、患者の行動が過剰に制限されがちです。
「危ないからベッドの上にいてください」「ナースコールで呼んでください」という言葉は、患者の自立性を少しずつ奪っていきます。
〇ベッドという重力からの解放
私たちは普段、意識せずとも重力に抗して体を支えることで、筋力や骨密度を維持しています。
しかし、ベッド上で寝ている時間が長くなると、この重力負荷が極端に減少し、筋肉や骨は急速に弱っていきます。
宇宙飛行士が宇宙空間で筋力低下に見舞われるのと同じ原理が、病院のベッドの上で起こっているのです。
〇管理された環境と刺激の欠如
病院は、消灯時間や食事が決められ、人間関係も医療者や他の患者に限られるなど、非常に管理された環境です。
自宅で送っていたような、変化に富んだ生活とは大きく異なります。
このような単調で刺激の少ない環境は、認知機能や意欲の低下を招きやすく、精神的な活力を削いでいきます。
〇「病人」という役割への過剰適応
周囲から「病人」として扱われ、身の回りのことを過剰に手伝われるうちに、患者自身も「自分は何もできない病人だ」と思い込んでしまうことがあります。
これを「学習性無力感」と呼びます。
自分でできることまで他者に委ねる習慣がついてしまい、心身の機能がさらに低下するという悪循環に陥るのです。
このように、治療のために最適化された入院環境は、皮肉にも人間の生活機能を維持するという観点からは、多くの危険性をはらんでいると言えます。
HADを引き起こす三大要因
HADは単一の原因で起こるのではなく、身体、精神、そして環境という複数の要因が複雑に絡み合って発症します。ここでは、その主要な原因を三つの側面に分けて詳しく解説します。
身体的要因:動かさないことが引き起こす体の悲鳴
(1)筋力低下と廃用症候群(Disuse Syndrome)
HADの最も根源的な原因が、活動量の低下によって引き起こされる「廃用症候群」です。
特に深刻なのが筋力の低下です。
健康な成人であっても、絶対安静の状態が1週間続くと筋力は10~15%低下し、3~5週間で約50%にまで半減するという驚くべきデータがあります。
高齢者の場合、その減少率はさらに高く、一度失った筋肉を取り戻すには、休んでいた期間の何倍もの時間と努力が必要となります。
特に衰えやすいのが、太ももやお尻といった下半身の大きな筋肉(抗重力筋)です。
これらの筋肉は、立ち上がる、歩く、姿勢を保つといった基本的な動作に不可欠であり、その衰えは直接的にADLの低下に繋がります。
この筋肉がやせ衰えた状態を「サルコペニア」と呼び、HADの温床となります。
(2)多岐にわたる身体機能の悪化
廃用症候群の影響は、筋力低下だけにとどまりません。
〇関節拘縮
関節を動かさないでいると、周囲の組織が硬くなり、関節の可動域が狭くなります。
膝や股関節が伸びなくなり、歩行が困難になるケースは少なくありません。
〇骨粗鬆症
骨は、歩行などによる適度な負荷がかかることで強度を保ちます。
ベッド上での生活ではこの負荷がなくなるため、骨がもろくなり、わずかな衝撃でも骨折しやすくなります。
〇起立性低血圧
長期間寝ていると、自律神経の調節機能が乱れ、急に立ち上がった際に血圧が下がり、めまいや立ちくらみを起こしやすくなります。これが転倒の恐怖心に繋がり、さらなる活動低下を招きます。
〇心肺機能の低下
全身の持久力が低下し、少し動いただけでも息切れや動悸がするようになります。
〇血栓塞栓症
足の血流が悪くなることで血の塊(血栓)ができ、それが肺の血管に詰まる「エコノミークラス症候群」のリスクが高まります。
(3)栄養状態の悪化という土台の崩壊
身体を維持し、回復させるためには適切な栄養が不可欠です。
しかし、入院中は食欲不振に陥りやすく、栄養状態が悪化するケースが頻繁に見られます。
〇食欲不振
環境の変化によるストレス、疾患そのものの影響、治療の副作用などで食事が進まなくなることがあります。
また、病院食が口に合わないといった問題も少なくありません。
〇低栄養
食事量が減ると、エネルギーはもちろん、筋肉の材料となるたんぱく質が不足します。
たんぱく質が足りなければ、いくらリハビリをしても筋肉は作られません。
血液中のアルブミン値(低栄養の指標)が低い患者は、HADを発症しやすいことが知られています。
〇脱水
高齢者はもともと体内の水分量が少なく、のどの渇きも感じにくいため、意識しないと容易に脱水状態に陥ります。
脱水は、せん妄や臓器機能の低下を引き起こす原因となります。
精神・認知の要因:見えない心の機能低下
(1)せん妄(意識の混乱)
HADの引き金として極めて重要なのが「せん妄」です。せん妄とは、病気や薬剤、環境の変化などが原因で生じる一時的な意識の混乱状態です。
症状:時間や場所が分からなくなる(見当識障害)、話のつじつまが合わない、幻覚が見える、興奮して大声を出す(過活動型せん妄)、逆にぼんやりして活気がなくなる(低活動型せん妄)など、症状は多彩です。
特に低活動型せん妄は「おとなしくなった」と見過ごされやすく、注意が必要です。
〇原因
慣れない病室、睡眠不足、痛み、脱水、感染症、手術、特定の薬剤などが複雑に絡み合って発症します。
〇影響
せん妄状態の患者は、点滴を自己抜去したり、ベッドから転落したりする危険性が高いため、行動制限が強化されがちです。
これにより活動量が激減し、廃用症候群が急速に進行します。
(2)意欲の低下とうつ状態
入院生活は、患者から社会的役割や生きがいを奪いがちです。「病気なのだから安静にしていなければ」という思い込みや、将来への不安、孤独感から、何事にもやる気が起きなくなることがあります。
このようなアパシー(無気力)やうつ状態は、リハビリテーションへの参加意欲を削ぎ、自ら動こうとする気持ちを失わせます。
身体機能が十分に残っていても、「動きたくない」という精神状態が、結果的に身体機能の低下を招いてしまうのです。
(3)睡眠障害
夜間の物音、ナースコールの音、同室患者のいびき、頻回の体温測定や点滴交換など、病院の夜は安眠を妨げる要因に満ちています。
質の良い睡眠がとれないと、日中の覚醒レベルが下がり、活動性が低下します。
また、疲労が回復せず、心身の機能低下に拍車をかけることになります。
医療体制・環境による影響:安全と自立のジレンマ
(1)安全管理の徹底がもたらす弊害
医療現場では、患者の安全確保が最優先されます。
特に「転倒・転落」は骨折などの重大な事故に繋がるため、厳重な対策が取られます。
しかし、その対策が時として過剰な安静指示や身体拘束に繋がり、患者の活動機会を奪う結果を招くことがあります。
安全を守るための行為が、長期的に見て患者の自立を損なうというジレンマが存在するのです。
(2)多剤服用(ポリファーマシー)のリスク
高齢者は複数の疾患を抱えていることが多く、多くの種類の薬を服用している場合があります。
これをポリファーマシーと呼びます。
薬の種類が増えれば増えるほど、副作用のリスクは高まります。
特に、眠気を誘う薬、血圧を下げる薬、精神に作用する薬などは、ふらつきや注意力の低下を招き、転倒やせん妄の原因となり得ます。
(3)専門職間の連携不足
医師は疾患の治療、看護師は日々のケア、リハビリ専門職は機能訓練と、それぞれの専門性は高いものの、患者の「生活全体」を俯瞰し、活動性をいかに維持・向上させるかという視点が共有されていない場合があります。
多忙な病棟業務の中で、患者一人ひとりの離床や活動を促す時間を十分に確保することが難しいという現実的な問題もあります。
HADを発症しやすい人とは?知っておきたいリスク因子
HADは誰にでも起こりうるものですが、特に発症しやすい「ハイリスク群」が存在します。
以下の因子に当てはまる場合、入院前から注意が必要です。
〇高齢(特に75歳以上)
加齢に伴い、筋力、バランス能力、認知機能などの身体的・精神的な予備能力(ストレスに対する抵抗力)が低下しているため、入院というストレスの影響を非常に受けやすい。
〇フレイル・サルコペニア
入院前から「フレイル(虚弱)」と呼ばれる、心身の活力が低下した状態にある人や、筋肉量が減少した「サルコペニア」の状態にある人は、HADの最たる予備軍です。
〇低栄養状態
体重減少が見られたり、血清アルブミン値が低かったりするなど、すでに入院前から栄養状態が悪い場合。
認知症や軽度認知障害(MCI)の既往:環境の変化に対応する能力が低く、せん妄を発症しやすい。
また、リハビリの内容を理解したり、意欲を維持したりすることが難しい場合がある。
〇入院前からのADL低下
すでに杖を使っていたり、歩行に介助が必要だったりするなど、入院前の自立度が低いほど、さらなる機能低下が起こりやすい。
〇複数の疾患(併存疾患)
多くの病気を抱えていると、それだけ全身状態が悪化しやすく、治療も複雑になりがちです。
〇多剤服用(ポリファーマシー)
前述の通り、多くの薬剤を服用している場合。
抑うつ、不安などの精神症状:もともと抑うつ傾向や不安が強い人は、入院によるストレスで精神的に不安定になりやすく、活動意欲が低下しやすい。
〇緊急入院や長期入院
予定された入院よりも、突然の入院の方が心の準備ができておらず、ストレスが大きい。
また、入院期間が長引けば長引くほど、廃用症候群のリスクは増大します。
これらのリスク因子を複数持つ場合は、入院の初期段階から特に積極的なHAD予防策を講じる必要があります。
HADがもたらす深刻な影響 失われるのは機能だけではない
HADの影響は、単に「歩けなくなる」といった身体機能の問題にとどまらず、本人、家族、そして社会全体に重くのしかかります。
本人への影響:尊厳と希望の喪失
〇生活の質の(QOL)の劇的な低下
自宅に退院できず、介護施設への入所を余儀なくされるケースは少なくありません。
住み慣れた我が家を離れ、自由が制限された生活を送ることは、大きな精神的苦痛となります。
〇自己肯定感の喪失と社会的孤立
「人の世話にならなければ生きていけない」「家族に迷惑をかけている」といった自己否定の感情に苛まれます。趣味や友人との交流といった社会参加の機会も失われ、孤独感が深まります。
〇再入院リスクの増大
機能低下により、転倒や誤嚥性肺炎などを起こしやすくなり、再入院を繰り返すという負のスパイラルに陥りがちです。
家族への影響:突然始まる介護という現実
〇介護負担の増大
退院後、家族は突如として介護の担い手となることを求められます。
食事、排泄、入浴などの身体的介助は、精神的にも肉体的にも大きな負担です。
〇経済的負担
介護用品の購入、住宅改修、介護サービスの利用など、経済的な負担が増加します。
場合によっては、家族が介護のために仕事を辞めざるを得ない「介護離職」に至ることもあります。
〇生活の一変と精神的ストレス
家族自身の時間や生活が大きく制限され、将来への不安やストレスから、家庭内の関係が悪化することもあります。
社会への影響:医療・介護制度の逼迫
〇在院日数の長期化
機能が回復しないため退院できず、ベッドを長期間占有することになり、急性期医療の効率を低下させます。
〇医療費・介護費用の増大
HADを発症した患者は、退院後も継続的な医療や介護サービスを必要とするため、国民医療費や介護保険財政を圧迫する大きな要因となります。
〇地域医療・介護資源の圧迫
介護施設や訪問サービスの需要が増大し、地域における介護資源の不足に拍車をかけます。
具体的な事例から学ぶHAD

◇事例1:80代女性(肺炎で入院)
入院前は一人暮らしで、近所のスーパーへ買い物に行くなど自立した生活を送っていた。
しかし、肺炎で2週間入院。治療中はベッド上安静が中心で、食事もベッドサイドで済ませていた。
肺炎は治癒し退院の許可が出たが、いざ立ち上がろうとすると足がふらつき、数メートル歩くだけで息が切れてしまう。
入院中に廃用症候群が進行し、退院時には室内での移動にも手すりや杖が必須となり、買い物や調理はヘルパーの支援が必要になった。
◇事例2:70代男性(軽度の消化管出血で入院)
現役で農業を営み、体力には自信があった。
内視鏡による止血術後、安静目的で数日間ベッド上で過ごした。夜間にトイレに起きようとした際、慣れない環境と点滴ルートが邪魔で混乱し、転倒。大腿骨を骨折し、緊急手術となった。
長期のリハビリが必要となり、退院後も農業への復帰は困難となった。
この事例では、元の疾患は軽度であったにもかかわらず、入院中のせん妄と転倒が連鎖し、深刻なHADを引き起こした。
HADは予防できる! 多職種で取り組む包括的アプローチ
HADは非常に深刻な問題ですが、決して避けられない運命ではありません。
適切な知識と介入によって、そのリスクを大幅に減らすことが可能です。
予防の鍵は、本人・家族、そして医療スタッフがそれぞれの立場で役割を果たし、連携することにあります。
本人・家族ができること〔入院生活の「受け身」からの脱却〕
意識改革 「安静は治療」の常識を疑う
まずは、「入院中は安静にしているのが一番」という考えを改めることが重要です。
もちろん、病状によって安静が必要な時期はありますが、状態が許す限り「動けることは自分で行う」「できるだけ座る・立つ・歩く」という意識を持つことが、予防の第一歩
入院中のセルフケア
〇ベッド上での運動
医師や看護師に許可を得た上で、足首を回す、膝の曲げ伸ばしをする、お尻に力を入れるなど、寝たままできる簡単な運動をこまめに行う。
〇離床の習慣化
ベッドの背をできるだけ起こして過ごす時間を長くする。
可能であれば、ベッドサイドの椅子に座って食事を摂る、歯を磨くなど、離床の機会を積極的に作る。
〇栄養の確保
食欲がなくても、食べやすいもの、栄養価の高いものを少しでも口にする。
特に筋肉の材料となるたんぱく質(肉、魚、卵、大豆製品など)を意識して摂る。
栄養補助食品の活用も有効です。
〇精神的な健康の維持
家族や友人と電話や面会で会話し、社会とのつながりを保つ。
新聞を読む、ラジオを聴く、趣味の編み物をするなど、ベッドサイドでできる楽しみを見つける。
〇家族の関わり方
家族は、心配のあまり何でも手伝ってしまいがちです。しかし、それが本人の自立性を奪っている可能性もあります。
本人が安全にできる範囲のことは、時間がかかっても見守り、自分でやってもらう「見守る勇気」が大切です。
また、入院中の本人の様子の変化(ぼんやりしている時間が増えた、話がかみ合わないなど)に気づいたら、すぐに看護師に伝えることも重要です。
医療スタッフができること〔多職種連携による早期介入〕
現代のHAD予防は、特定の職種だけが頑張るのではなく、チームで行うのが主流です。
〇早期リハビリテーションの徹底
「治療が始まってからリハビリを検討する」のではなく、「入院直後からリハビリを開始する」という考え方が重要です。
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が早期に介入し、患者一人ひとりの状態に合わせた機能訓練プログラムを立案・実施します。
〇多職種による包括的アセスメントと情報共有
医師、看護師、リハビリ専門職、管理栄養士、薬剤師、医療ソーシャルワーカーなどが定期的にカンファレンスを開き、患者の情報を共有します。
栄養状態はどうか、せん妄のリスクはないか、退院後の生活環境はどうかなど、多角的な視点からリスクを評価し、チームとしての方針を決定します。
〇看護師による生活リハビリの実践
看護師は24時間患者に最も近い存在です。
治療の介助だけでなく、排泄や更衣、食事といった日常生活の場面で、患者の「できる能力」を最大限に引き出すようなケア(自立支援ケア)を意識することが、HAD予防に絶大な効果を発揮します。
〇環境調整
時計やカレンダーを分かりやすい場所に置く、日中はカーテンを開けて光を浴びてもらう、夜は静かな環境を整えるなど、せん妄を予防するための環境作りも重要です。
〇ACEユニット(Acute Care for Elders Unit)の導入
これは、高齢者医療に特化した病棟モデルです。
高齢者の特性を理解した多職種チームが配置され、日中の離床を促す共有スペースがあったり、早期からのリハビリや栄養管理が徹底されたりするなど、HAD予防のための環境が整っています。
社会的な支援〔シームレスな医療と介護の連携〕
HAD予防は、病院内だけで完結するものではありません。
〇退院支援・退院前カンファレンスの重要性
患者が退院後も安全に、そして活発に生活を続けられるように、入院中から医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーが介入します。
退院前に本人・家族、病院スタッフ、地域の介護サービス担当者が一堂に会し(退院前カンファレンス)、必要なサービス(訪問リハビリ、デイケア、福祉用具のレンタルなど)を調整し、切れ目のない支援体制を構築します。
〇地域包括ケアシステムの活用
住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の中で、HAD予防は重要な柱の一つです。
地域の医療機関、介護事業所、行政が連携し、地域全体で高齢者の機能低下を防ぐ取り組みが求められます。
HAD研究の最前線と今後の展望
HADに対する認識の高まりとともに、その予防や治療に関する研究も日進月歩で進んでいます。
〇早期離床プログラムの効果
かつては絶対安静が常識だった集中治療室(ICU)においても、人工呼吸器を装着した重症患者に対して早期からリハビリを行う「早期離床プログラム」の有効性が証明され、世界的に普及しています。
〇栄養と運動の相乗効果
運動療法と、BCAA(分岐鎖アミノ酸)などの特定の栄養素を組み合わせることで、筋力低下をより効果的に防げるという研究報告が多数あります。
〇テクノロジーの活用
ウェアラブルセンサーを用いて患者の活動量を客観的にモニタリングし、離床が不足している患者にアラートを出すシステムや、タブレット端末を用いた認知機能トレーニングなど、ICTを活用した新たな介入方法も開発されています。
〇予防モデルの構築
日本老年医学会などが中心となり、HAD予防のための診療ガイドラインを作成し、全国の医療機関へその普及啓発を進めています。
今後は、個々の患者のリスク因子に応じて最適な予防プログラムを提案する「個別化医療」や、退院後も継続的にフォローアップできるような遠隔リハビリテーションシステムの発展が期待されています。
日常生活から始めるHAD予防:入院前からできること
HADのリスクを減らすためには、入院前から「フレイル」を予防し、心身の予備能力を高めておくことが最も効果的です。
ウォーキングなどの有酸素運動に加え、スクワットなどの軽い筋力トレーニングを習慣にしましょう。
筋肉は最高の「貯金」です。
〇バランスの取れた食事
特に、筋肉の材料となるたんぱく質を毎食しっかり摂ることを心がけましょう。
〇社会参加
趣味の会やボランティア活動などに参加し、人との交流を保つことは、心と脳の健康を維持するために非常に重要です。
万が一入院することになった場合も、本記事で紹介した「本人・家族ができること」を思い出し、主体的に入院生活に関わっていく姿勢が、あなたの未来を大きく左右します。
まとめ
入院関連機能障害(HAD)は、治療対象の病気とは別に、「入院」という環境そのものが引き起こす、静かで、しかし深刻な機能障害です。
それは、高齢者だけの問題ではなく、いつ誰の身に降りかかってもおかしくない現代医療の影の部分と言えるでしょう。
しかし、強調したいのは、HADは「予防できる障害」であるということです。
(「過度な安静」の危険性を知り、入院中も可能な限り体を動かし、栄養を摂り、精神的な活力を維持する)……本人と家族がこの意識を持ち、医療者が多職種で連携して早期から介入することで、そのリスクは確実に減らすことができます。
「病気を治すための入院」が、「新たな介護の始まり」になってしまわないように。
この記事が、HADという問題への理解を深め、あなたとあなたの大切な人が、入院後も自分らしい豊かな生活を送り続けるための一助となれば幸いです。
入院はゴールではなく、その先の生活へと続く、回復への重要なステップなのです。

 掲載をご希望の施設様
掲載をご希望の施設様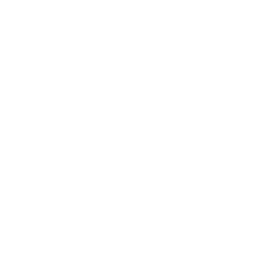 介護
介護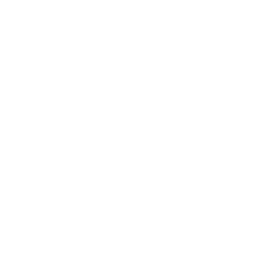 介護用具
介護用具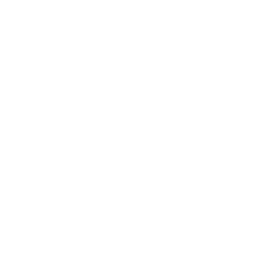 運営会社
運営会社