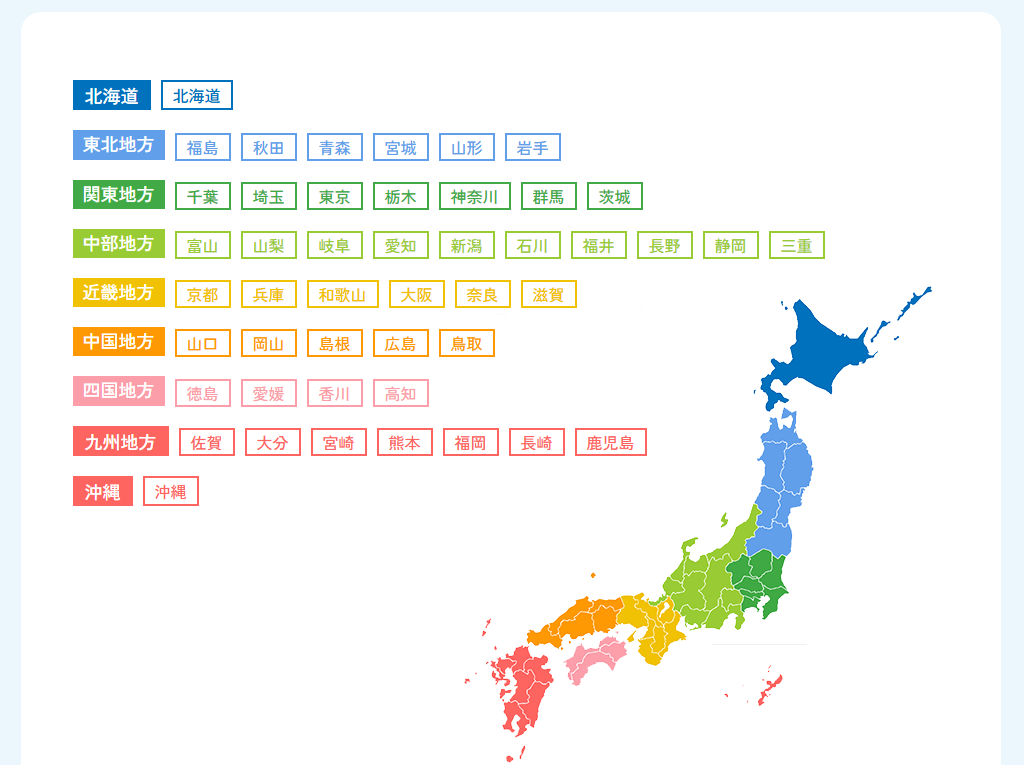親が認知症を発症すると、金融機関による口座凍結が行われる可能性があります。
口座凍結は本人の財産を守るための措置ですが、家族にとっては大きな問題となることがあります。
本記事では、認知症による凍結資産リスクについて、その対処法と予防策を詳しく解説します。
認知症と口座凍結の関係性
認知症による凍結資産リスクは、認知機能の低下に伴い発生します。
認知症は病名ではなく、認識力や記憶力、判断力に障害が起きている状態を示す総称です。
金融機関は、顧客の財産を保護する義務があるため、認知症の症状が確認された場合、口座凍結という手段を取ることがあります。
凍結の主な理由は以下の通りです。
- 判断能力の低下による財産管理の困難
- 本人の意思確認が困難になること
- 悪徳商法などの被害防止

認知症による凍結資産リスクは、本人だけでなく家族の生活にも大きな影響を与える可能性があるため、早期の対策が重要となります。
認知症の進行度合いによっては、日常的な金銭管理が困難になり、生活に支障をきたす可能性もあります。
金融機関による認知症の察知方法
認知症による凍結資産リスクを理解するには、金融機関がどのように認知症を察知するかを知ることが重要です。
主な察知方法は以下の通りです。
- 家族からの申し出
- 窓口での本人の様子
- 施設入所手続きの際の情報
金融機関の職員は、顧客との日常的なやり取りの中で、認知機能の低下を示す兆候に注意を払っています。
例えば、同じ質問を繰り返したり、書類の記入に著しい困難を示したりする場合、認知症の可能性が疑われます。
また、普段と異なる大きな金額の引き出しや、不自然な頻度での来店なども、注意すべきサインとされています。
早期に気づくことで、適切な対応が可能となり、認知症による凍結資産リスクを軽減できる可能性があります。
一方で、プライバシーの観点から、金融機関が顧客の認知症の有無を積極的に確認することは難しい面もあります。
口座凍結がもたらす影響
認知症による凍結資産リスクが現実となり、口座凍結が行われると、以下のような影響が生じます。
- 預金の引き出しが不可能になる
- 口座の解約ができなくなる
- 家族による代理手続きが認められない
口座凍結がもたらす影響について詳しく解説します。
生活費や介護費用の支払いが困難になる
認知症により資産が凍結されると、本人の生活費や介護費用の支払いが困難になる可能性があります。
また、家族が立て替えて支払いを行っても、後に返還を受けられない可能性もあります。
年金の受け取りができなくなる
口座凍結により年金の受け取りができなくなる可能性もあります。
年金は多くの高齢者にとって主要な収入源であり、受け取れなくなることは生活に直接的な影響を与えます。
公共料金などの自動引き落としができなくなる
口座凍結により、公共料金や医療費の自動引き落としができなくなります。
公共料金などの自動引き落としができなくなると、日常生活の維持が困難になる可能性があります。
クレジットカードの利用が停止される可能性がある
口座凍結に伴い、クレジットカードの利用が停止される可能性があります。
クレジットカードが停止してしまうと、緊急時の支払いや日常的な買い物が制限されることがあります。
認知症によって凍結された口座の解除手順







認知症による凍結資産リスクが現実となった場合、口座の凍結解除が必要となります。
凍結された口座を解除するには、主に以下の2つの方法があります。
- 口座の解除手順
- 成年後見制度の活用方法
詳しく見ていきましょう。
口座の解除手順について
口座の解除手順は、通常以下のステップを踏みます。
- 本人の認知症の診断書を用意する
- 金融機関に相談し、必要書類を確認する
- 申請書類を提出し、審査を受ける
- 金融機関の判断により、口座の凍結が解除される
ただし、本人の判断能力が著しく低下している場合、解除が困難な場合があります。
金融機関によっては本人の意思確認が難しい場合、凍結解除に応じないこともあります。
凍結解除に応じない場合は、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
成年後見制度の活用方法とは







成年後見制度の活用方法は、認知症による凍結資産リスクに対する有効な解決策の一つです。
成年後見制度を利用するには下記の手順が必要です。
- 家庭裁判所に申立てを行う
- 調査官による調査と審理を経る
- 成年後見人等が選任される
- 審判が確定し、法定後見が開始される
成年後見制度を利用することで、成年後見人が本人に代わって財産管理や契約を行うことができるようになります。
成年後見制度が利用できれば、凍結された口座からの引き出しや解約が可能になります。
ただし、制度の利用開始までには3〜4カ月程度かかるため、早めの準備が重要です。
また、成年後見人の報酬が必要となる場合もあるため、費用面での検討も必要です。
事前にできる凍結防止策
認知症による凍結資産リスクに備えるため、事前に取れる対策があります。
主な対策として以下の2つがあります。
- 家族信託制度
- 任意後見制度
早い段階から準備することで、将来的な問題を回避できる可能性が高まります。
家族信託制度とは







家族信託制度は、本人に代わって財産の管理を家族に託せる制度です。
この制度を利用することで、認知症による口座凍結が起きても、預貯金の引き出しなどを託された家族が行うことができます。
家族信託制度の主な特徴は以下の通りです。
- 財産管理を特定の家族に任せることができる
- 信託契約に基づいて財産管理が行われる
- 柔軟な資産運用が可能
ただし、この制度はあくまでも財産管理に限定されており、介護サービスの契約などは代理できません。
また、信託設定にかかる費用や、税務上の取り扱いについても注意が必要です。
家族信託制度は、認知症による凍結資産リスクに対する有効な予防策の一つとして考えられています。
特に、複雑な資産構成を持つ場合や、事業承継を考えている場合に有効な選択肢となります。
任意後見制度とは







任意後見制度は判断能力が不十分になる前に、財産管理や介護サービスの契約締結などを任せる後見人を決めて依頼する制度です。
任意後見制度を利用することで、認知症により銀行口座が凍結された場合も、本人に代わって口座から預貯金の引き出しが可能になります。
任意後見制度の主な特徴は以下の通りです。
- 本人が信頼できる人を後見人に選ぶことができる
- 財産管理だけでなく、身上監護も含めた幅広い支援を受けられる
- 本人の意思を尊重した支援が可能
ただし、本人の判断能力が十分なうちに契約を結ぶ必要があります。
また、任意後見人の選定や、契約内容の決定には慎重な検討が必要です。
将来的な認知症リスクに備えて、比較的若いうちから利用を検討することも一案です。
特に、家族関係が複雑な場合や、専門的な資産管理が必要な場合には、有効な選択肢となります。
介護費用の立替えと相続時の扱い
認知症による凍結資産リスクにより口座が凍結されると、家族が介護費用を立て替えることがあります。
- 立て替え費用の扱い
- 遺産分割協議での対応
- 対策と注意点
詳しく見ていきます。
立て替え費用の扱いについて
立て替えた介護費用は、「日々の生活でかかる費用」つまり生活費という扱いになります。
生活費は家族であれば本人の代わりに支払って当然とみなされる費用になるため、たとえ領収証などを全て保管していたとしても、相続のときにその額を差し引いてもらえるかは明確ではありません。
遺産分割協議での対応とは
遺産分割協議での対応とは、寄与分として認めてもらうよう他の相続人に相談することです。
しかし、立て替えたと認めてもらえない可能性もあります。







特に、他の相続人との関係が良好でない場合や、立て替えの経緯が不明確な場合は、認められにくい傾向にあります。
介護費用を立替える際の注意点
認知症により口座が凍結されても、成年後見制度等を利用し、介護費用はできるだけ本人の財産で賄うことが賢明です。
また、介護費用の立替えを行う場合は、以下の点に注意することをおすすめします。
- 立替えの記録を詳細に残す
- 可能な限り、他の家族や相続人の了解を得る
- 介護の内容や必要性を明確にする
- 専門家(弁護士や税理士)に相談する
対策を取ることで、将来的な相続時のトラブルを回避できる可能性が高まります。
まとめ:認知症による資産凍結リスクへの備え方
認知症による凍結資産リスクに備えるには、早期対策が重要です。
家族信託制度や任意後見制度の活用、成年後見制度の理解など、事前準備をしておきましょう。
また、口座凍結時の対処法や介護費用の立替に関する知識も必要です。
家族間での情報共有と話し合い、専門家への相談も大切です。


適切な準備と対策で、本人の意思を尊重しつつ、適切な財産管理と介護を実現できます。

 掲載をご希望の施設様
掲載をご希望の施設様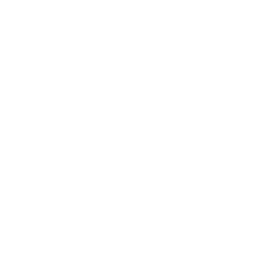 介護
介護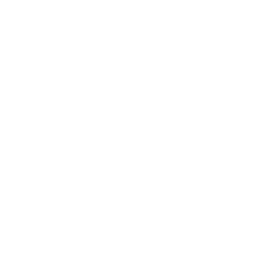 介護用具
介護用具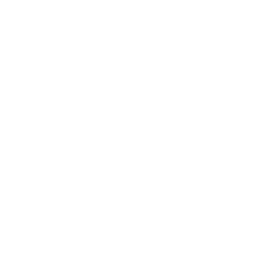 運営会社
運営会社